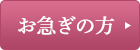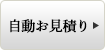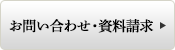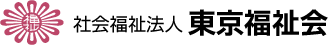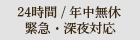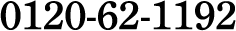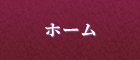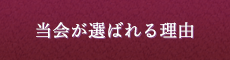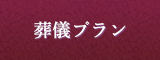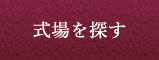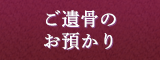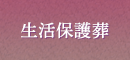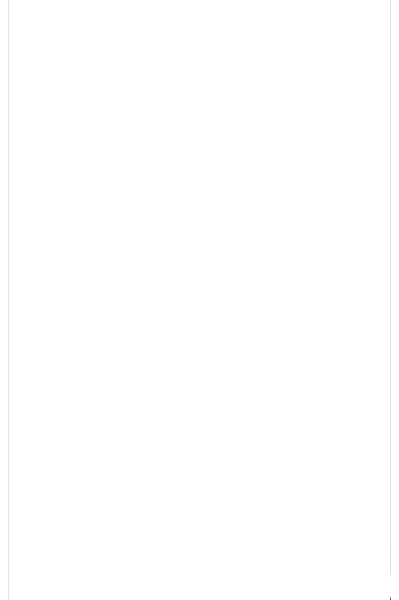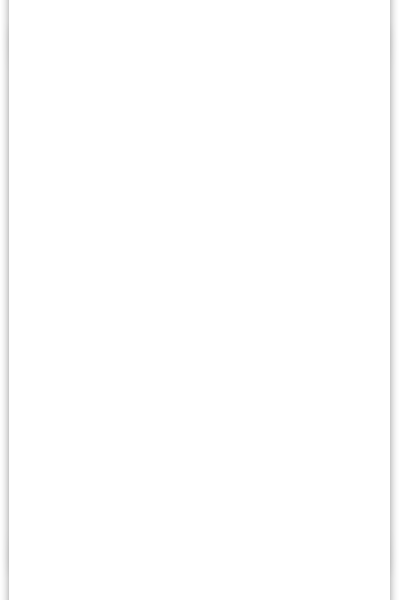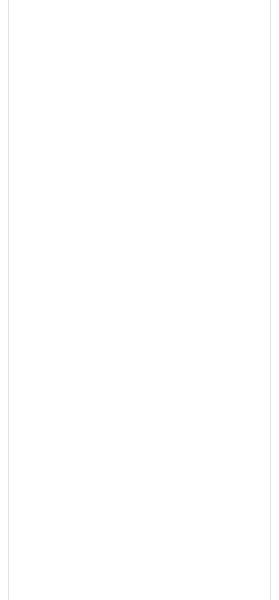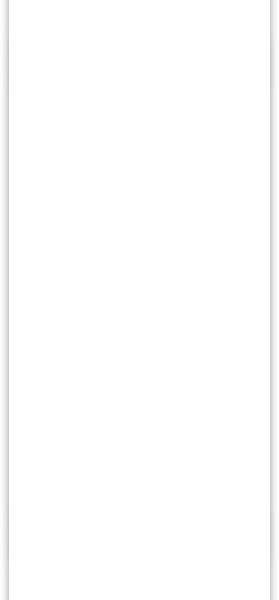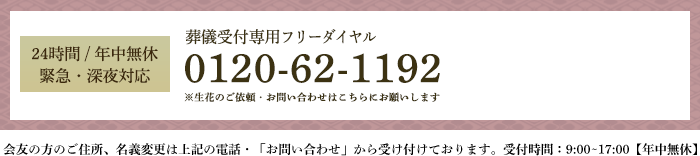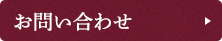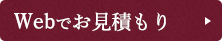生活保護葬について

葬祭扶助とは、生活保護法第十八条で定められるものです。
下の枠内は生活保護法第十八条です。
葬祭扶助
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
| 一 | 検案 | |
|---|---|---|
| 二 | 死体の運搬 | |
| 三 | 火葬又は埋葬 | |
| 四 | 納骨その他葬祭のために必要なもの | |
| 2 | 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、 前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 |
|
| 一 | 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 | |
| 二 | 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 | |

簡単にいうと、生活に困窮し葬儀費用が払えない人のために、国が葬祭に関わる必要最低限の内容を行ってくれるという制度です。
葬儀についての実務は委託された葬儀社が行い、国から葬儀社に費用が支払われるのが一般的です。
この葬祭扶助制度を適用した葬儀を、当会では「生活保護葬」と呼んでいます(福祉葬、生活保護葬など、葬儀社によって呼び名は変わります)。
また葬祭扶助が適用されるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
| 1. | 葬儀を執り行うかた(条文の”扶養義務者”のことです)が、困窮状態で葬祭費の支払いができないとき |
|---|---|
| 2. | 故人が単身者で身寄りがなく、葬祭費にあてられるような金品を遺しておらず、生活保護を受給していたとき |
葬祭扶助受給に関するQ&A
遺族は生活保護を受けていますが、故人は受けていなかった場合は?
故人の遺した遺留金が葬祭費に満たない場合、残りの部分について葬祭扶助が適用されます。
故人は生活保護を受けていましたが、
遺族には収入や資産がある(葬儀費用が出せる)場合は?
葬祭扶助は適用されません。
また、火葬費用等を葬祭扶助で出してもらい、お通夜や告別式など葬儀式については自分たちで払うので行いたい、と希望されるご遺族様が時折いらっしゃいます。お気持ちは理解できるのですが、あくまでも葬祭扶助は「火葬費用もままならない」方に対して支給されるものです。葬儀式代金が支払えるのであれば、そのお金をまず火葬費用等に充てていただくことになります。
その他、故人様・ご遺族様の状況によって様々な対応が考えられます。
また、状況調査等に日数を要する場合がありますので、葬祭扶助の受給については、事前にお住まいの地域の福祉事務所へお問い合わせいただく事をお勧めいたします。
葬祭扶助葬の内容について
葬祭扶助の内訳は、死亡の確認(検案)・故人の移動費用・火葬費用・納骨費用となります。
セレモニー(通夜・葬儀式等)は行われず、火葬のみのいわゆる「直葬」となります。